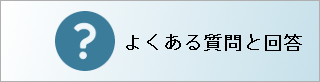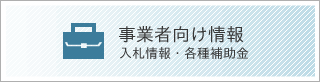更新日:2025年8月19日
ここから本文です。
ヘルパンギーナに関する警報が発令されました
感染症発生動向調査事業による2025年第27週(6月30日~7月6日)の「ヘルパンギーナ」患者の定点当たり発生報告数が、県の警報発令基準である6.00を超えたことから7月8日に伊集院保健所管内にヘルパンギーナに関する警報が発令されました。
今後、さらに流行が拡大することも予測されることから感染防止・感染拡大防止対策の徹底と今後の発生動向に注視していただくようお願いします。
ヘルパンギーナについて
ヘルパンギーナとは
発熱とともに、のどに痛みと水疱(すいほう)が現れる「夏かぜ」の一種です。ヘルパンギーナは乳幼児を中心に、主に夏に流行します。感染症発生動向調査によると、5歳以下が全体90%以上を占めます、病気の原因となるウイルスは主にコクサッキーウイルスA群ですが、コクサッキーウイルスB群、エコーウイルスが原因となることもあります。
症状
感染してから2日から4日後に、突然の発熱に続いて、のどに痛みと水疱(すいほう)が現れます。発熱は1日から3日続き、食欲不振、全身のだるさ、頭痛などを起こします。一般的には経過は良好で、2日から3日以内に回復します。しかし、合併症として、熱性けいれん、脱水症、小児ではまれに髄膜炎や心筋炎などの注意が必要です。
感染経路
感染経路は、主に経口感染(糞口感染:便と一緒に排せつされたウイルスが口に入って感染すること)、接触感染、飛まつ感染です。
急性期には、のどからウイルスが排せつされるため、せきをした時のしぶき(飛まつ)により感染します。また急性期から回復期(発症後2週間から4週間程度)にかけて、便からウイルスが排せつされるため、便が付いたおむつや下着などに触れた後は、しっかり手洗いしてください。
治療法
基本的には軽い症状の病気のため、経過観察を含め、症状に応じた治療となります。
しかしながら、まれに髄膜炎や心筋炎などが起こる場合があるため、経過観察をしっかりと行いましょう。
以下の症状がみられた場合は、医療機関への受診をご検討ください。
- 高熱が出る
- 発熱が2日以上続く
- 嘔吐する
- 頭を痛がる
- 視線が合わない
- 呼びかけに答えない
- 呼吸が速くて息苦しそう
- 水分がとれずにおしっこがでない
- ぐったりとしている
5.予防と対策
基本的な感染対策を生活習慣にしましょう。日頃から手洗い、うがいといった感染対策を生活習慣にすることが大切です。
ヘルパンギーナは、発症後2週間から4週間頃まで便からウイルスが排せつされるため、発症した乳幼児のおむつ交換を行うときは、排せつ物を適切に処理し、流水と石けんでしっかりと手洗いをしてください。
6.発生状況
国内では毎年5月頃より増加し始め、7月頃にかけてピークを形成し、8月頃から減少を始め、9月から10月にかけてほとんど見られなくなる傾向があります。感染症発生動向調査によると、5歳以下が全体の90%以上を占めます。
7.関連サイト
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください